たとえ企業との契約が業務委託であっても、労働者であるかどうか、つまり労働者性については、実態をもって判断されます。
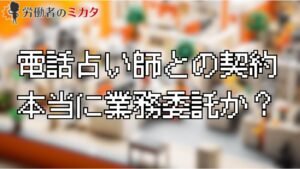
「業務委託」でも実態が雇用に近ければ保護が及ぶ
使用従属性は、かみ砕くと「指揮監督下の労働かどうか」「報酬が労務の対価か」という二本柱です。
具体的には、
- 時間・場所の拘束(シフト・在席義務・遅刻早退の扱い)
- 業務遂行の具体的な指示命令(例えば“会話禁止”“服装・行動細則”“懲戒”)
- 代替性の有無(他人に代わってもよいのか)
- 報酬の支払い方法(時間・分単価は労務対償性が濃い)
などを総合評価します。
これに、専属性(兼業禁止・名称使用の強い制限)や、道具・設備の支配管理の態様といった補強事情が乗ります。厚労省の最新資料も、これらを整理して実務指針を示しています。
「店内会話は絶対禁止」+「服装・行動を細管理」は“内部規律”の強さを示す
安全確保のルールはどの契約形態にもあり得ますが、違反即処分の懲戒ベースで常時監視を前提とする運用は、請負より雇用に近い管理と評価されやすく、使用従属性を補強します。通達・注意・指導履歴があるなら、その具体性(いつ/誰から/どの手段で/何を言われたか)を記録しましょう。これは、後述の「解雇・雇止め」や「偽装請負」の論点とも密接に結びつきます。
「担当時間枠」+「10分/1分単価」は“労務の対価”の色合いが濃い
発注側が担当時間枠を決め、在席や応対を求め、さらに報酬が時間(分)単価で支払われる構造は、成果請負というより労務提供の色が濃いと評価されがちです。遅刻・中抜けの扱い、交代の自由度、代替可能性の有無など、拘束の具体をメモ化してください。
兼業の全面禁止や名称使用の広い制限は“専属性”を強める
独立自営としての自由度が低いほど、労働者性の判断は強まりやすい。退職後・終了後まで広範囲・長期間に及ぶ名称使用の制限は、(公序良俗の観点で)必要最小限性や期間・範囲の限定が求められる領域でもあります。実務上は、混同防止など正当目的に即した限定が鍵です。
解雇・雇止め・中途解除の基礎ルール
労働者性が認められる場合、解雇は労働契約法16条により「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合は無効」。また労基法20条で、30日前の解雇予告(または予告手当)が原則です。厚労省の公式Q&Aやリーフレットも同旨を明確にしています。
労働契約法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働基準法
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
一方で労働者性が否定され、フリーランス(業務委託)のままでも、2024年11月1日に施行された特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス新法」)が走ります。第3条(条件明示)、第4条(受領日起算60日以内の支払期日設定・支払)、第5条(不当な受領拒否・減額等の禁止)に加え、第16条で6か月超の継続委託の中途解除・不更新には30日前予告と理由開示(請求があれば)が定められました。公正取引委員会の年報や厚労省の公表資料が条文の要点を整理しています。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)
第三条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。
2 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。(報酬の支払期日等)
第四条 特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた日。次項において同じ。)から起算して六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 前項の場合において、報酬の支払期日が定められなかったときは特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日が、同項の規定に違反して報酬の支払期日が定められたときは特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過する日が、それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなす。
3 前二項の規定にかかわらず、他の事業者(以下この項及び第六項において「元委託者」という。)から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務(以下この項及び第六項において「元委託業務」という。)の全部又は一部について特定受託事業者に再委託をした場合(前条第一項の規定により再委託である旨、元委託者の氏名又は名称、元委託業務の対価の支払期日(以下この項及び次項において「元委託支払期日」という。)その他の公正取引委員会規則で定める事項を特定受託事業者に対し明示した場合に限る。)には、当該再委託に係る報酬の支払期日は、元委託支払期日から起算して三十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
4 前項の場合において、報酬の支払期日が定められなかったときは元委託支払期日が、同項の規定に違反して報酬の支払期日が定められたときは元委託支払期日から起算して三十日を経過する日が、それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなす。
5 特定業務委託事業者は、第一項若しくは第三項の規定により定められた支払期日又は第二項若しくは前項の支払期日までに報酬を支払わなければならない。ただし、特定受託事業者の責めに帰すべき事由により支払うことができなかったときは、当該事由が消滅した日から起算して六十日(第三項の場合にあっては、三十日)以内に報酬を支払わなければならない。
6 第三項の場合において、特定業務委託事業者は、元委託者から前払金の支払を受けたときは、元委託業務の全部又は一部について再委託をした特定受託事業者に対して、資材の調達その他の業務委託に係る業務の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。(特定業務委託事業者の遵守事項)
第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条において同じ。)をした場合は、次に掲げる行為(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒むこと。
二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること。
三 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
四 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること。
五 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
2 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不当に害してはならない。
一 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した後(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた後)に給付をやり直させること。(解除等の予告)
第十六条 特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。次項において同じ。)をしようとする場合には、当該契約の相手方である特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも三十日前までに、その予告をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
2 特定受託事業者が、前項の予告がされた日から同項の契約が満了する日までの間において、契約の解除の理由の開示を特定業務委託事業者に請求した場合には、当該特定業務委託事業者は、当該特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なくこれを開示しなければならない。ただし、第三者の利益を害するおそれがある場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
「電話一本で即日終了」はNGになり得る
労働者と評価されるなら労契法16条+労基法20条の問題で、無効リスクが大きい。フリーランス扱いでも、新法16条により30日前予告と理由開示(請求時)が原則。告知手段や到達の証拠(メール・書面・通話記録)は、のちの交渉で極めて有用です。
「規約違反の理由を示さない終了」は説明責任の問題
雇用なら懲戒の相当性や説明が問われ、フリーランスでも理由開示の制度設計がなされています。まずは簡潔でよいので書面で理由開示を請求し、同時に就業実態の記録を整理しましょう。
「更新を重ねて通算6か月超」も対象になり得る
基本契約+個別契約で更新を積み上げるケースでも、通算で6か月以上の継続的委託に当たれば、予告・理由開示の適用対象になり得ます。公的資料を根拠に形式より実態で確認をしましょう。
取引条件・支払サイト・減額禁止
第3条(条件明示)は、給付内容・報酬額・支払期日などを書面または電磁的方法で直ちに明示する義務。請求があれば紙交付にも応じます。第4条(支払期日)は、受領日から起算して60日以内のできる限り短い期間で支払期日を設定・支払すること。第5条は不当な受領拒否・減額・返品の禁止です。いずれも、「雇用でないから自由」という従来の見方を改めさせる重要な規律です。
「月末締・翌々々月末払い」は危険サイン
受領起算で60日超の支払期日設定は第4条に抵触するおそれ。自分の請求書(受領日)と実際の支払日を時系列表で突き合わせ、60日ルールに収まっているか点検しましょう。
「検収済みなのに一方的に減額」は不当減額の疑い
第5条は、責めに帰すべき事由がないのに受領拒否・減額することを禁じています。減額の根拠・合意・手続きを文書で確認し、修正依頼を冷静に出すのが第一歩です。
再委託チェーンでの“遅延横流し”
上流の支払期日が明示されている場合、再委託分はその日から30日以内の支払いが要件となる場面があります。契約書の条項と実運用の差を洗い出すと、改善交渉の足場が整います。
監視カメラ・会話監視と個人情報保護法
監視カメラの画像は個人情報に該当し得ます。利用目的の特定・周知、目的内利用、保存期間の最小化、アクセス権限の限定などは、個人情報保護委員会のパンフレットでも繰り返し示される基本原則です。防犯目的で設置したカメラを規律監視に広く転用する運用は、目的外利用の疑義が生じ得るため、掲示・規程・保存期間・アクセス管理を見える化し、必要最小限性を検証すべきです。
「防犯カメラでおしゃべり監視」は目的適合性が焦点
当初の掲示文言や社内規程と実運用が整合しているか、保存期間や閲覧権限が過大ではないかを点検。改善要請は短く事実ベースで。
「長期保存・広範アクセス」には最小限性の観点から見直しを
保存が長期に及ぶ、閲覧者が多すぎる。こうした運用は、必要最小限性の説明が難しくなります。保存期間の短縮とアクセスログ管理をセットで提案しましょう。
請負?派遣?「現場指揮・時間管理」の境界(偽装請負の注意点)
厚労省は、「労働者派遣か請負かの区分は実態で判断」すると明記しています。発注者が現場で個々人に直接指示し、出退勤や時間管理まで掌握する態様は、形式が請負でも派遣に近いと評価されやすい。偽装請負は厳しく問題化します。最新の疑義応答集や実務ガイドもこの点を繰り返し周知しています。
「現場責任者が個人に直接指示」は区分を曖昧にする
請負の独立性を担保するなら、指示は受託側の管理者経由に通す、成果基準を明確にする等の運用整理が必要です。逆に、出退店カメラで在席管理までして個人を直接統制すれば、区分誤りの疑いが強まります。
「シフト・就業時間を発注側が固定」は要注意
誰が時間管理の主体なのかは重要。請負事業主が自ら就労管理を行っていない実態は、疑義応答集でも偽装請負の典型例として警告されています。
空調・衛生・設備を「誰が支配・管理」しているか
場所・設備を発注側が実質支配し、そこで就業させているなら、雇用でなくても信義則上の安全配慮義務が問題となり得ます。最高裁は、元請の支配下で働く下請労働者に対して元請に安全配慮義務があると認めた判決を示しています(平成3年4月11日第一小法廷)。作業場所・設備・工具を元請が管理し、事実上の指揮監督があった事案で、安全確保配慮の義務が肯定されました。空調不良の長期放置、衛生の不備は、こうした観点から改善を求め得る領域です。
「空調が数年壊れたまま」なら
熱中症や体調悪化のリスクは予見可能で、回避可能な対策(修繕・代替設備)があるなら、放置は不適切となり得ます。修繕要請の履歴や現場写真を日付付きで積み上げてください。
「共用部の清掃が行き届かない」と転倒・衛生リスク
転倒・感染等のリスクは、設備・環境の支配管理の度合いに応じて、発注側に是正の要請が可能。委託側・受託側の役割分担と、要請に対する応答記録を残すことが肝です。
競業避止・名称使用制限・高額違約金の見直し(公序良俗・民法90条/420条)
競業避止は、保護すべき正当利益があるか、対象業務・地域・期間が必要最小限か、そして代償(補償)の有無が有効性のポイント。終了後も恒久的・包括的に名称使用や実績表示を禁ずるのは、過度拘束として無効・限定解釈の可能性があります。例えば違約金の一律高額設定などは、実損との均衡を欠くと民法90条(公序良俗)や420条(賠償額の予定)の観点から減縮・無効が争点化し得る領域です。ここは交渉で限定(期間・地域・業務)し、代償を設ける等の落とし所を探るのが現実的です(条文の趣旨に照らし、必要最小限性と均衡の確保を明示すると通りやすくなります)。
民法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
「疑いあり」のサインを見た時の実務ロードマップ
まずは証拠化から着手してください。担当枠の指示、会話禁止・服装等の通達、注意・処分の連絡、カメラの掲示や運用規程、支払明細と入金日、兼業制限の通達、空調・衛生の状態と要請履歴――これらを日付入りで残します。
次に、角を立てずにフリーランス新法の線から淡々と是正要請を行います。第3条(条件明示)に基づき、給付内容・報酬・支払期日の書面/電磁明示を依頼。第4条の受領日起算60日ルールに合わせて支払期日の再設定を求め、第5条の不当減額禁止を踏まえ、根拠のない減額の是正を要請します。6か月超の継続委託であれば、第16条に基づき30日前予告と理由開示の運用を確認。これらは雇用か否かの白黒をつける前でも出せる現実的な要求です。
そのうえで、実態として使用従属性が濃いと感じたら、労働基準監督署や労働局へ相談を。労働契約法16条(解雇権濫用法理)、労基法20条(解雇予告)等の適用可能性が具体的に検討されます。また、請負/派遣区分や現場指揮の問題は37号告示の資料に照らして整理すると、行政・事業者との共通言語ができます。監視カメラ運用は、個人情報保護委員会のパンフレットを根拠に、目的特定・目的内利用・保存期間・アクセスを可視化する方向で調整を。
交渉が難航する場合は、条項の見直しに焦点を移します。競業避止は対象・地域・期間の限定と代償を、名称・実績の表示は混同防止の観点に絞り込む整理を提案。違約金は均衡と根拠の提示を求め、過大なら公序良俗・賠償額の予定の観点から減縮を主張します。いずれも短く・事実ベースで伝えること、やり取りを記録することがコツです。

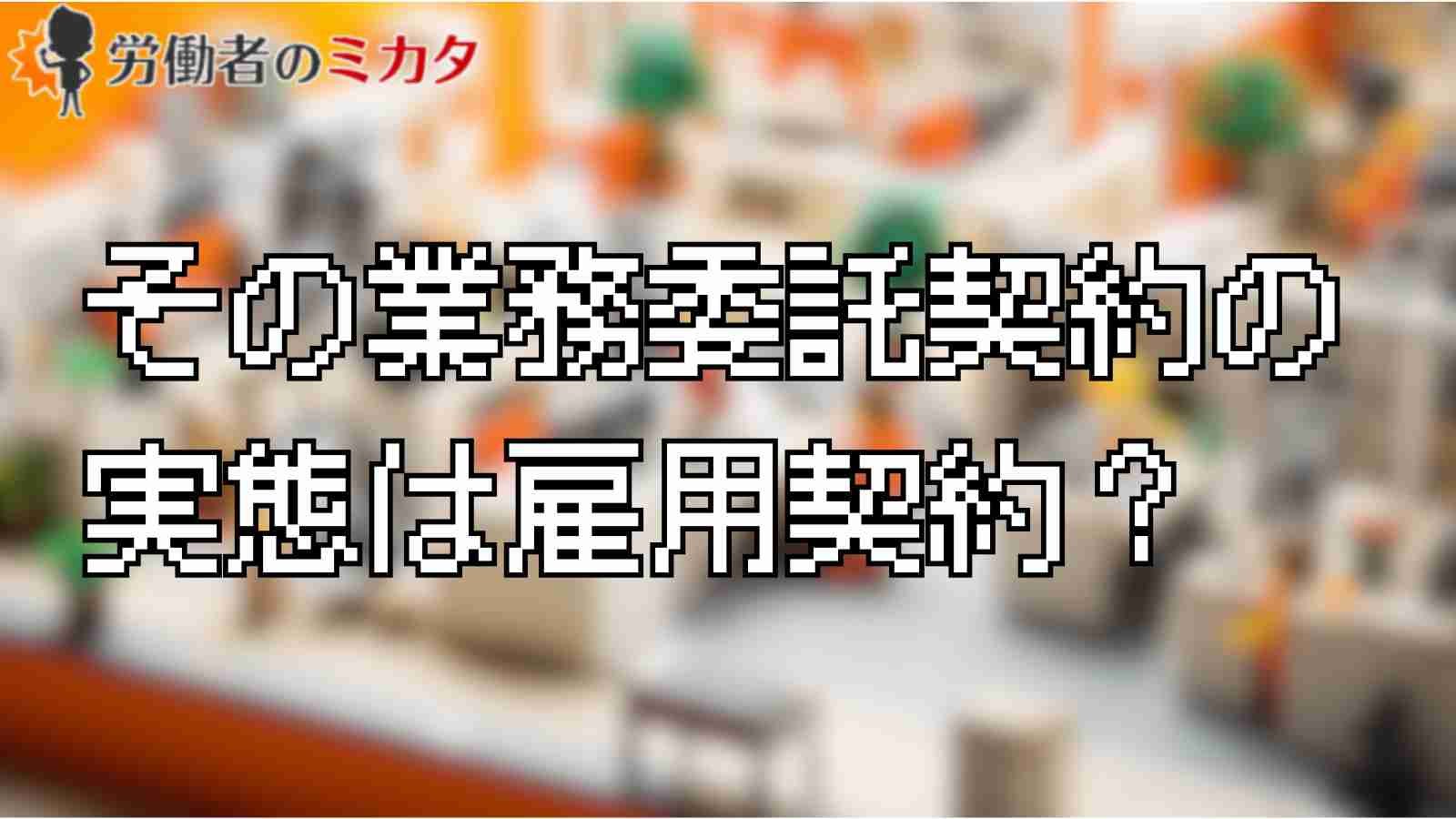

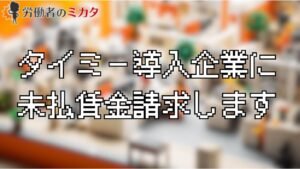

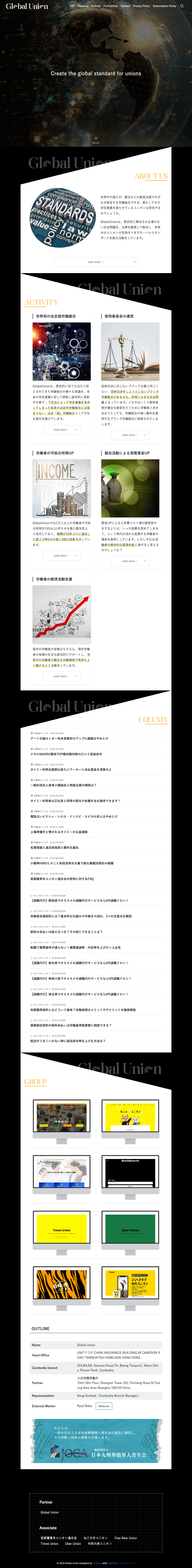
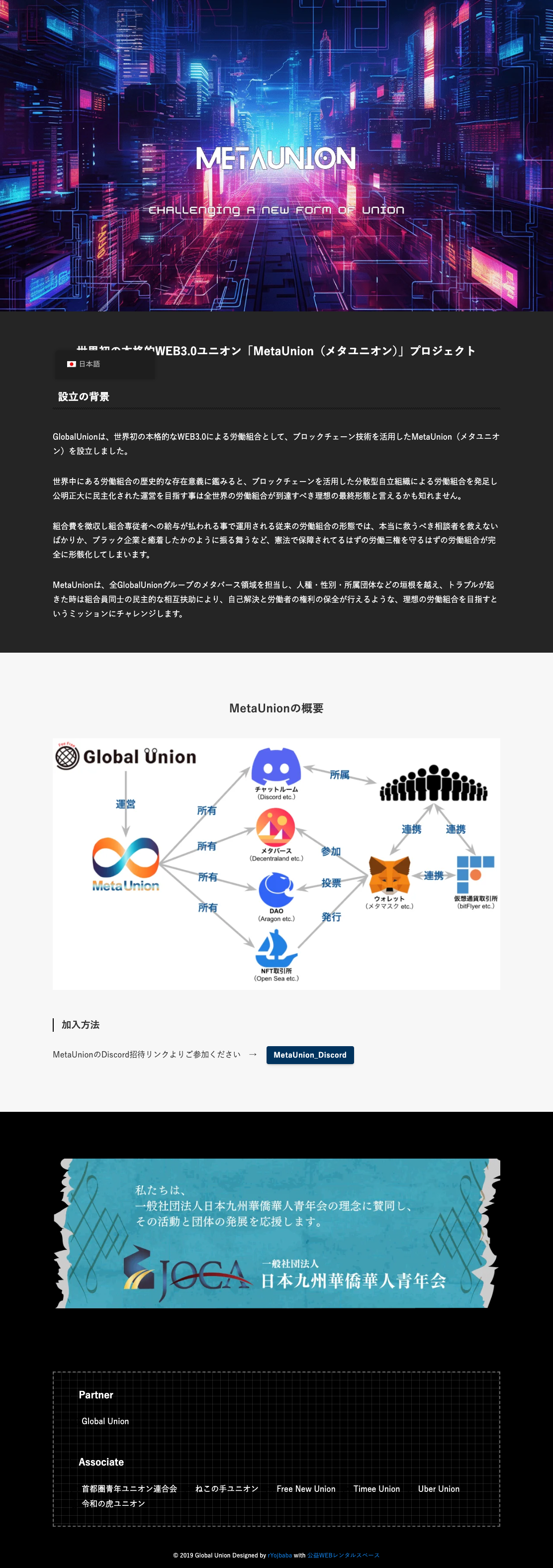
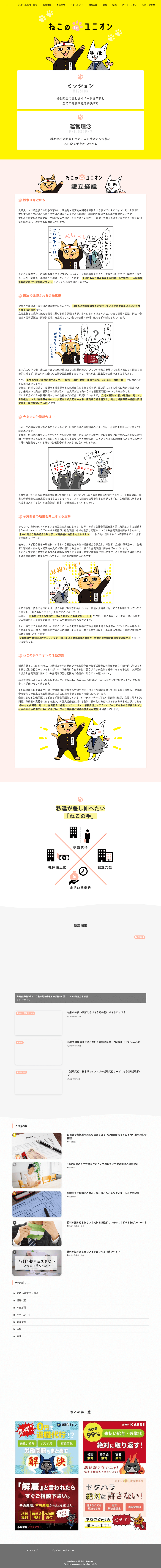
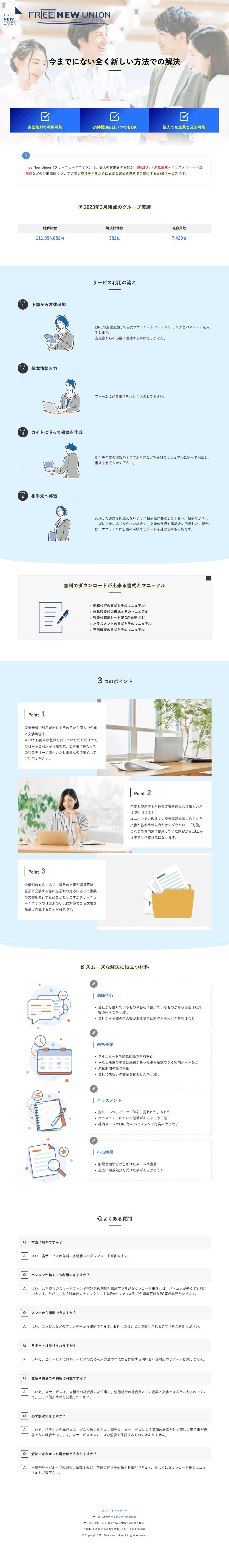
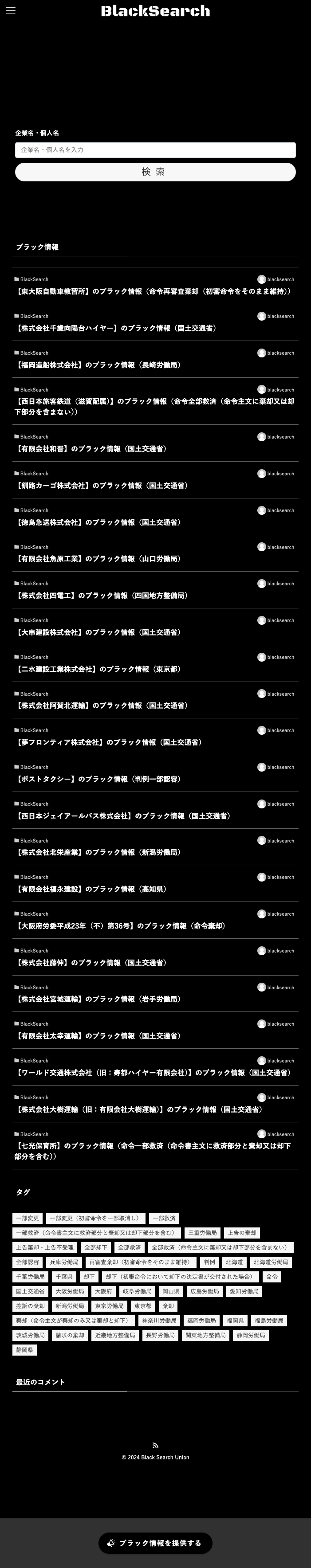
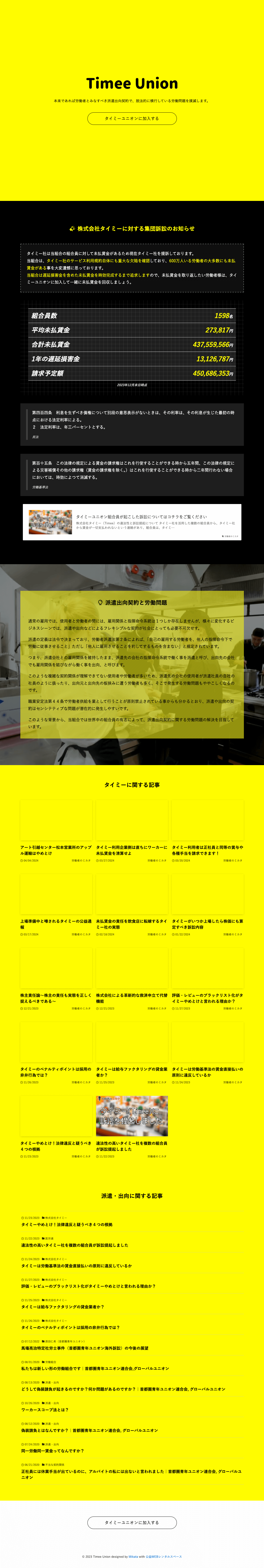

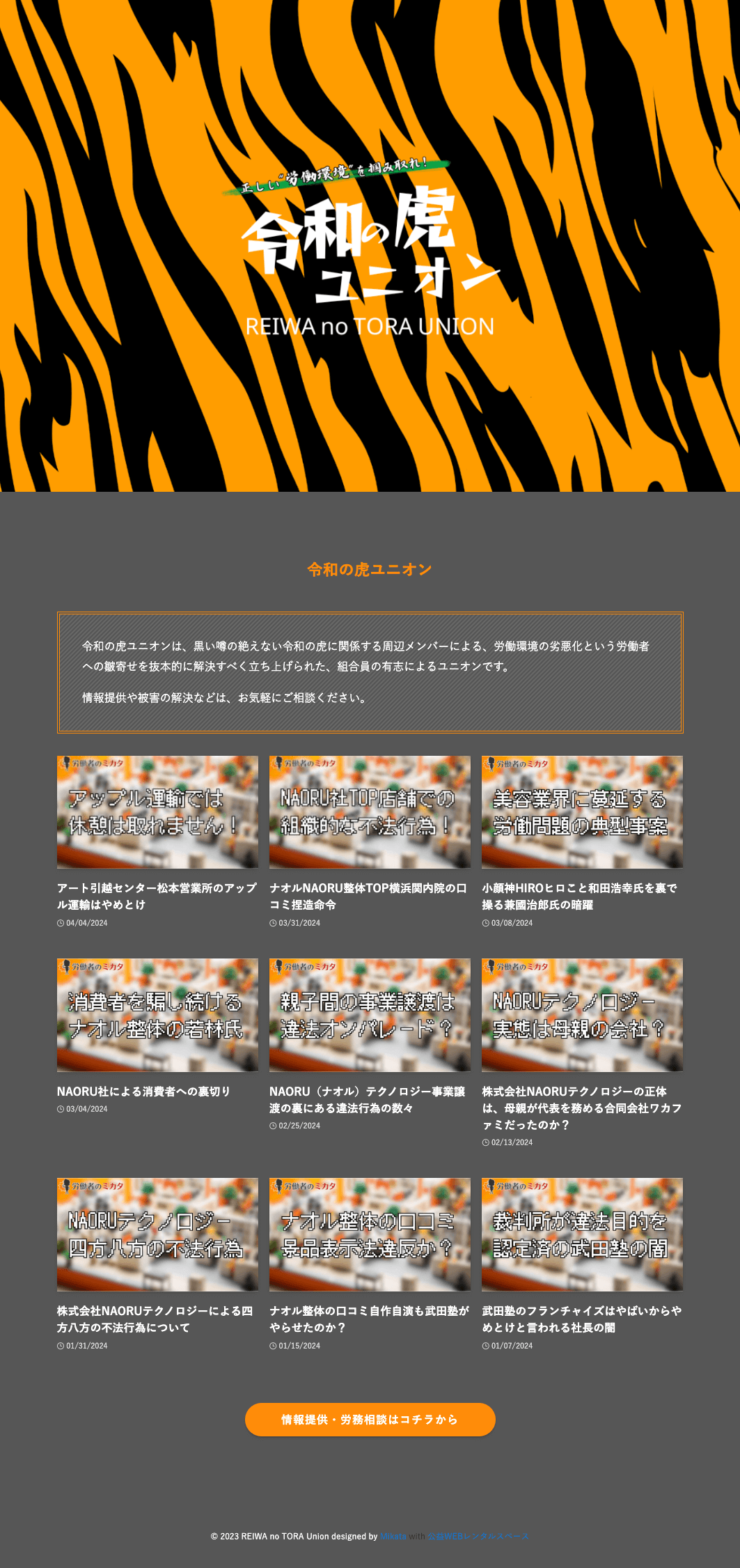
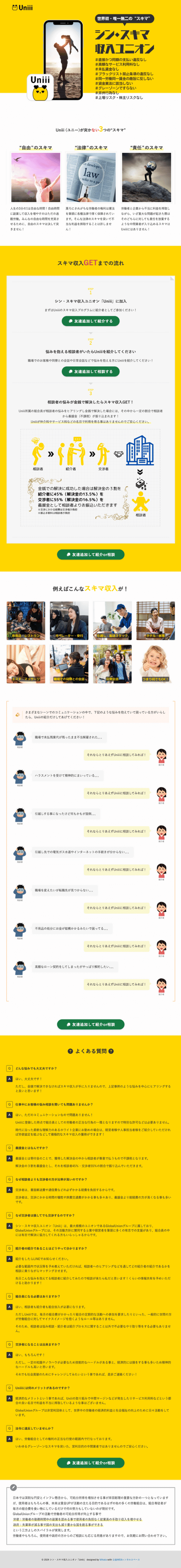
コメント