鳥取大学の事例(署名)を起点に、公益通報者保護法の本質的課題を突く
巨大組織の「沈黙の合意」を越えるために
当組合は、職場の中長期的な改善をめざし、組合員の安全と尊厳を最優先に据えます。本稿では、松江様の署名内容(鳥取大学でのパワハラ・賃金不払い等の是正・謝罪を求める呼びかけ)を問題視する組合員からの要望に基づき、「巨大組織におけるハラスメントの構造問題」と、「公益通報者保護法が現場で機能不全に陥る構造」について問題提起をしていきます。
1. 巨大組織におけるハラスメントは「いまも現在進行形」の社会問題
「沈黙の合意」が生み出す被害の長期化
巨大組織では、経営・人事・広報が強い裁量と情報コントロールを握るため、不正やハラスメントに関する内部情報が組織内で「沈黙の合意」に吸収されやすいです。被害は「個人対個人」の問題でなく、組織の意思決定と監督不全の問題です。
近年のジャニーズ事務所の性加害問題でも、「長年の沈黙」が被害の連鎖を許し、第三者調査の公表と社会的監視が入ってようやく再発防止と補償に向けた動きが始まりました。大規模組織×強大な評判資本が絡むと、被害の声はかき消されやすいという教訓です。
大学・病院等の公共性の高い組織ほど、透明性の欠如は致命的
公共性が高い組織での不正・ハラスメントは、労働者の権利侵害にとどまらず、公費や患者・学生の安全にも波及します。署名ページが指摘するような「調査体制が利害関係者で構成される」事態は、調査の独立性・公正性の要件に真っ向から反します。法定指針は、内部通報体制に幹部からの独立性確保と利益相反の排除を求めています。
公益通報者保護法は「ある」のに、なぜ現場で機能しないのか
入り口の問題:制度の認知不足と窓口の不可視化
消費者庁の就労者1万人調査によれば、内部通報制度を理解していない層は従業員規模「300人超〜1,000人以下」で57.6%、「5,000人超」でも47.7%に達します。さらに、内部通報窓口が未設置または認知されていない割合は「300人超〜1,000人以下」で65.4%、「5,000人超」でも45.7%。「どこに相談すればよいか分からない」が通報しない最大理由で、不利益取扱いへの不安も根強いことが示されました。
途中の問題:犯人探しと調査不全(兵庫県知事事案にみる失敗)
2024年の兵庫県庁内部告発問題では、通報内容の精査より「作成者探し」が先行した初動が強く批判され、県議会の第三者調査で「通報者探索は公益通報者保護法違反」と認定されました。これは制度趣旨(通報の萎縮防止)に反する典型例です。
出口の問題:是正・説明の欠落と不利益の発生
同調査では、相談・通報した人の17.2%が「後悔」。理由は「調査や是正が行われなかった」が最多で、不利益取扱いも無視できません。通報時は匿名希望が62.6%にのぼります。制度理解が高いほど「勤め先にまず通報」が選ばれる一方、理解が浅いほどSNS等へ流れやすい傾向も確認され、公正な内部プロセスの可視化が抑止・予防に直結します。
法制度の現状と根本課題
2022年施行の改正(令和2年改正)の射程
改正法は、大企業に内部通報体制の整備を義務付け、通報処理に関わる者へ守秘義務(違反に刑事罰)を課し、退職者(1年以内)・役員の保護に拡大、行政機関や報道機関への通報要件を明確化しました。「制度の骨組み」は整いました。
それでも止まらない「犯人探し」
現場の実情(兵庫県事案など)を受け、2025年改正はさらに、
- 通報者特定目的の行為を明示的に禁止
- 不利益取扱いの直罰化、通報後1年以内の解雇・懲戒は通報理由と推定(立証の転換)
- フリーランスまで保護拡大
- 体制整備義務への命令・罰則/立入検査
等を盛り込み、「抑止」と「救済」の実効性を高めました。とはいえ、施行・運用はこれからで、各組織の実務に落ちるまでギャップが残ります。
本質的な病巣は三つの「ねじれ」
権限のねじれ
窓口・調査の独立性が弱いと、人事権を持つ側が事実上の当事者になり、調査・是正が自家中毒に陥る。指針は独立性・利益相反排除を求めるが、実装の品質差が大きい。
情報のねじれ
通報者保護のため守秘が必要だが、透明性(進捗・結果説明)が乏しいと不信・後悔を生む。「適切な範囲の通知」は指針上の要請で、運用上の肝。
負担のねじれ
これまで不利益の立証負担は通報者側に偏重してきた。2025年改正の推定規定と直罰化は是正だが、現場の証拠管理・記録化が伴わなければ実効は上がらない。
労働組合からの制度運用への実務提言
通報者を保護し社会の健全な発展を目的とする趣旨に従い、労働組合の観点から下記を提言します。行政機関による誠実な運用に期待します。
独立調査の原則化
通報受付・調査・是正勧告は人事ラインから切り離し、利益相反排除を「形式」ではなく人選と手続で担保する(外部弁護士・第三者委の標準化)。
犯人探しの即時禁止の徹底
全管理職に通報者特定目的の行為の禁止を周知し、逸脱時は懲戒基準を明文化。通報対応者以外の独自調査を禁じる。
手続の可視化
受付→受理判断→初動調査→是正→フィードバックのタイムラインと責任者を明示。通報者への中間通知・結果通知の範囲を内規化。
不利益推定に耐える記録
会議体・人事判断・配置転換の意思決定ログを時系列で保全。反証責任が雇用主側に転換する前提で、通報前からの評価根拠も保存。
リテラシーとアクセス
就労者1万人調査が示した認知不足・窓口不可視を直視し、年1回の必修研修と匿名チャネル(外部委託ホットライン・24hウェブ)を整備。掲示・イントラ、給与明細同封の周知の仕組みを固定化。
鳥取大学の事例から見える「改善の勘所」
署名にあるような、賃金不払い・ハラスメント・利害関係者による調査といった疑義は、内部統制と通報体制の同時不全を示します。
- 制度面では、独立性・利益相反排除に反しうる構成は不可。
- 運用面では、通報者保護>組織防衛の優先順位が揺らぐと、犯人探し→萎縮→恒常化に陥る。兵庫県庁の事例は、その帰結の危険を示しました。
- 社会面では、ジャニーズ問題が示したとおり、透明性の欠如は被害の長期化と社会的信頼の喪失を招く。
「公益通報」は“組織のためにも”必要
松江様のように、不正を見て声を上げた人が苦しむ現実は、社会の至る所に潜在しています。巨大組織のハラスメントは、もはや個人の耐性に委ねてはならない「構造の病」です。
公益通報者保護法は、2022年施行の大改正、さらに2025年改正でようやく「犯人探しの明示的禁止」「不利益への直罰化」「立証の転換」といった核心に踏み込みました。あとは私たち一人ひとりと組織の運用です。
不正な組織を正し、労働環境の向上を実現するためには勇気が必要かもしれませんが、苦しんでいる方は決して一人ではありません。間違っていることは間違っていると、公益通報制度に則って通報しましょう。私たち労働組合は通報前の相談、証拠化、通報先の選択、通報後のフォローまで伴走します。


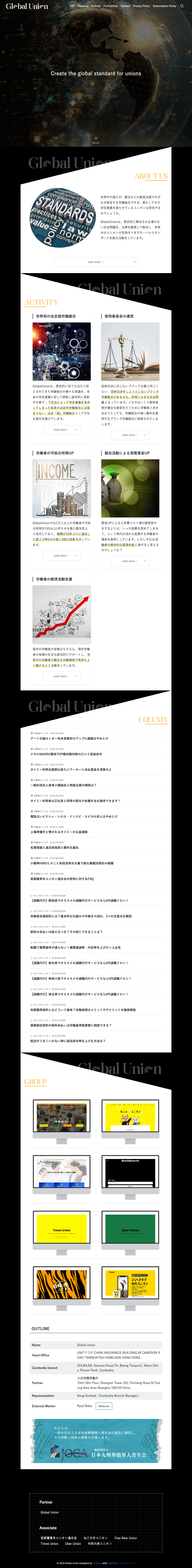
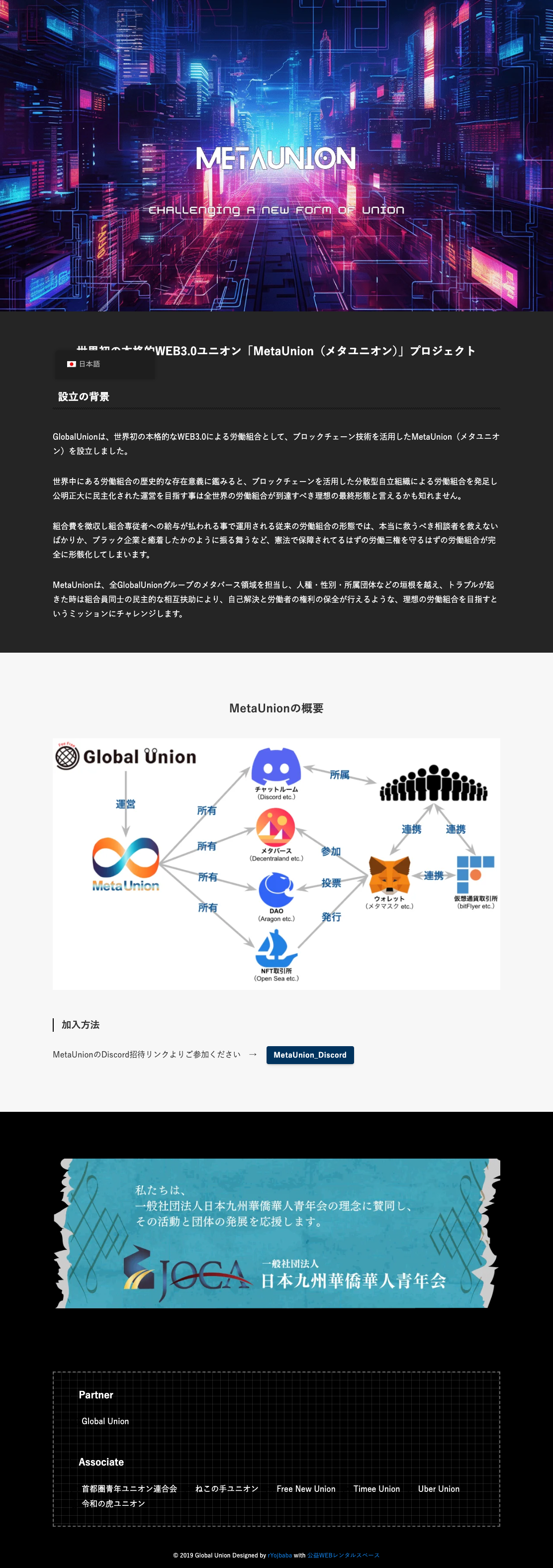
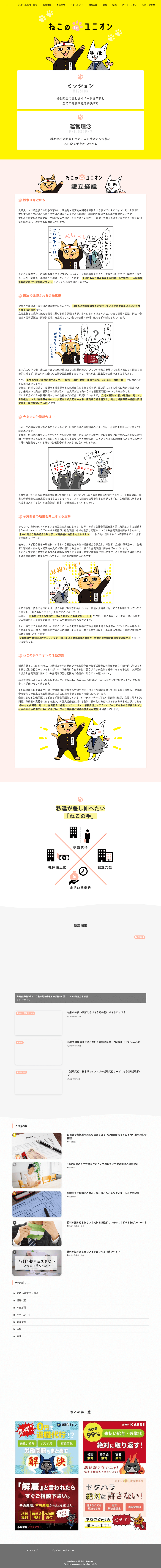
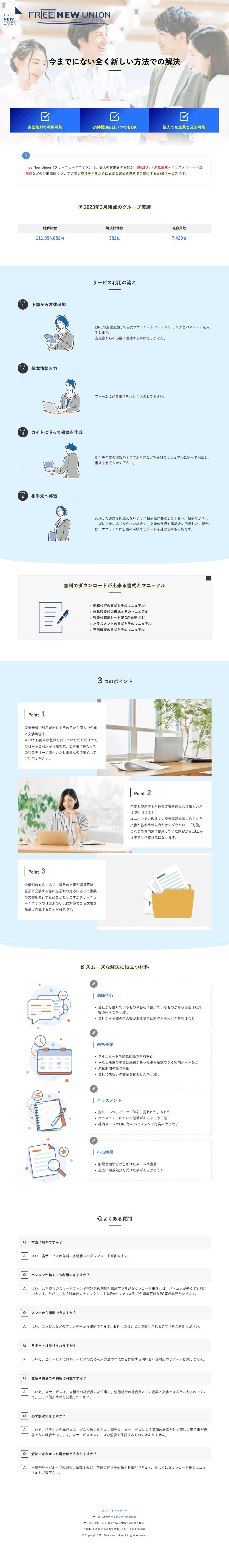
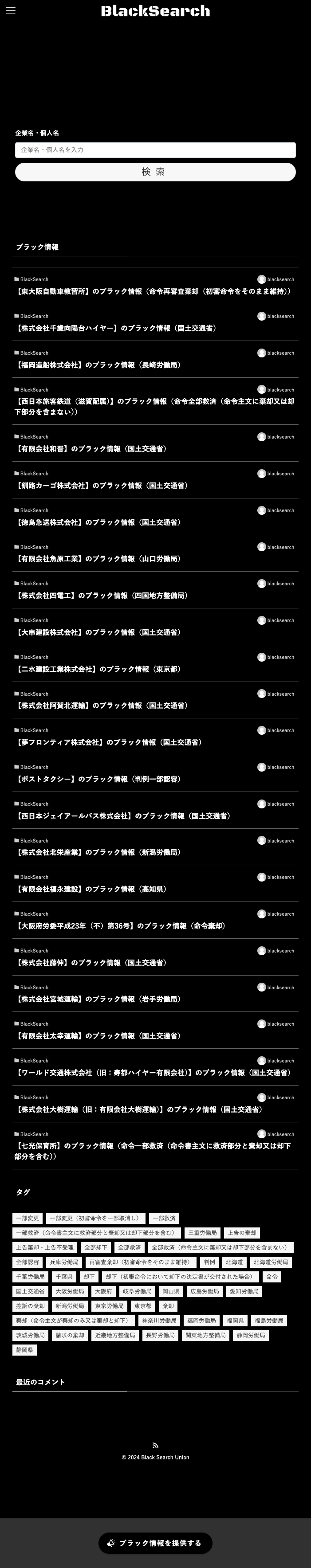
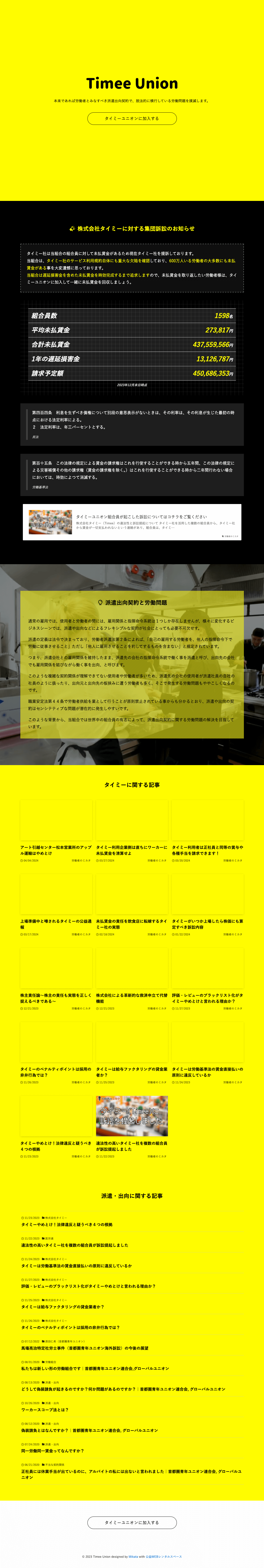

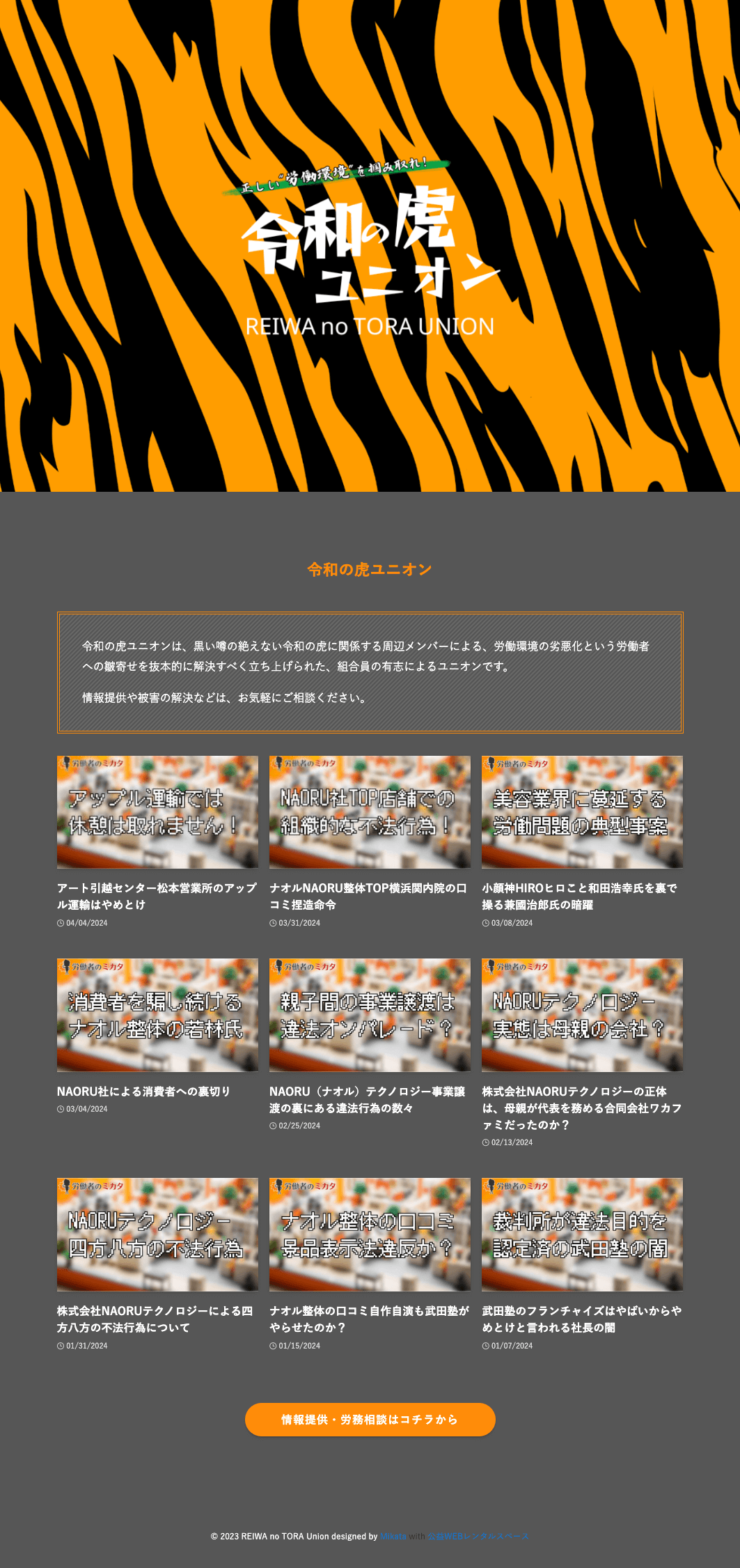
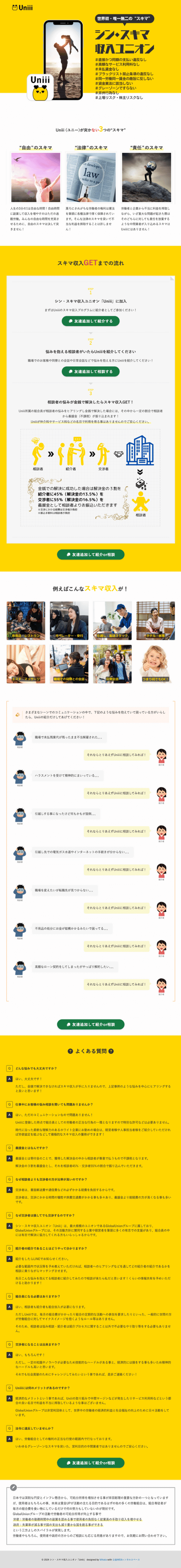
コメント