背景: リスキリング助成金制度と政府の方針転換
政府はDX人材育成や労働者のスキル転換(リスキリング)を推進するため、人材開発支援助成金(いわゆるリスキリング助成金制度)を拡充しています。岸田政権下で「5年間で1兆円投入」という大胆な計画が示され 、多くの企業がこの助成金を活用してリスキリングに取り組み始めました。実際、ある調査ではリスキリングに取り組む企業の68%が何らかの助成金を利用し、その89%が厚労省の人材開発支援助成金を活用していることが報告されています 。これは上場企業を含む多数の企業がこの制度に依存していることを示しています。
そうした中、厚生労働省は2025年度(令和7年)から人材開発支援助成金の申請手続きを大きく見直しました。従来は研修計画を事前に提出して労働局の審査・受理を受ける「計画届」制度がありましたが、2025年度より計画届提出時の審査・承認行為が廃止され、提出自体は受け付けるものの本格的な審査は支給申請時に一括実施する方式へ切り替えられたのです 。要するに、研修開始前の計画段階で行政による内容チェックが行われず、研修実施後の支給申請時になって初めて要件を満たすかの審査が行われることになりました 。厚労省自身、「計画届を提出したことをもって、助成金が確実に支給されるものではない」ことに留意し、特に初めて申請する場合は計画届提出前に十分相談するよう注意喚起しています 。
現場への影響: 不明確な運用と高いハードルによる不安定さ
制度設計の変更により、企業の現場には戸惑いと負担が生じています。事前審査がなくなったことで制度運用は不透明さを増し、現場担当者(従業員)は“手探り”のまま研修を進めざるを得ない状況です。以下に現場で指摘される主な問題点をまとめます。
制度内容が不明確
計画段階で行政の確認が得られないため、自社の研修計画が助成要件を満たしているかどうか事前に確証が持てません。厚労省も「助成金が確実に支給されるものではない」ことを明言しており 、企業側は常に不安を抱えたまま計画を進めることになります。結果として、制度の適用可否が研修実施後までわからないという不透明な運用になっています。
申請手続きのハードルが高い
助成金申請には多くの書類作成や厳格な要件確認が必要であり、手続きの煩雑さが現場担当者の大きな負担となっています。2025年の調査でも「85%の企業が申請時の負担を感じており、提出書類の煩雑さや支給要件の厳しさが主な課題」と報告されています 。事前審査の省略によって、こうした厳しい要件をすべて研修実施後にまとめてクリアしなければならないため、担当者の心理的・業務的ハードルは一層上がっています。
受理拒否・不支給のリスク
最終的な審査は支給申請時に一括で行われるため、せっかく計画どおり研修を実施しても助成金が支給されない(申請が却下される)リスクが常に付きまといます 。計画届の段階で不備や不適合を指摘してもらえない分、企業にとっては「やってみたが結局助成金が降りなかった」*という最悪の事態も起こりえます。このリスクは現場に不安定さをもたらし、制度運用への信頼性を低下させています。
上場企業の姿勢: 無批判な追随と改善要求の欠如
このように、制度内容の不明確さ、申請ハードルの高さ、結果の不確実性が重なり、現場では不安定で不透明な運用となっています。本来、助成金制度は企業の訓練投資を支援するための安心材料であるべきですが、現状では「下手をすると訓練コストを自社負担した上に助成も受けられないリスク」を現場従業員が背負わされている状況です。
しかしながら、こうした制度運用上の問題がありながらも、多くの企業(特に上場大企業)はこの助成制度を鵜呑みにして受け入れ、無批判に現場運用しているのが実態です。政府のリスキリング推進方針に呼応し、各社とも助成金を活用した研修計画を次々と打ち出していますが、その制度上の不備や現場への過重なしわ寄せに対して、公に疑問を呈したり行政に是正を求めたりする姿勢は殆ど見られません。
企業側が助成金を活用するのは当然の経営判断とも言えます。先述のように人材育成助成金は約9割の企業が利用する主要制度であり 、競合他社がそれによって人材投資コストを軽減している中、自社だけが利用しないのは経済合理性に反するでしょう。とはいえ、制度の恩恵に与ることばかりを優先し、その制度設計上の問題点について建設的なフィードバックを行わない態度には疑問が残ります。
本来、上場企業にはステークホルダー(従業員含む)への説明責任や、社会正義に反する慣行に異議を唱える責務があります。しかし現在まで、例えば経営者団体や産業界から「計画届段階での確認省略は現場に混乱を招くのではないか」「運用の明確化を図るべきだ」といった公式な提言がなされたという話題は聞こえてきません。多くの企業はお上の方針に追随するだけで、制度の問題点に目をつぶったまま現場に運用を丸投げしているように見えます。
制度を所管する行政に対し、利用者である企業側から改善要求やフィードバックがなされない状況は、結果的に現場従業員の不利益が放置されることを意味します。上場企業が率先して声を上げないことで、制度の不公正さが是正されないどころか、「問題は現場が工夫して乗り越えればよい」という誤ったメッセージを送ってしまっているのではないでしょうか。企業経営陣の姿勢が問われるべき状況です。
従業員への過度な負荷と法的リスク
現場レベルでは、助成金申請の準備・対応は主に人事部門や研修担当者といった一般従業員に委ねられるケースが多いでしょう。今回の運用変更により、そうした従業員へ過剰な業務負荷と責任の押し付けが発生している場合、企業には法的なリスクも生じます。日本の労働法制では、使用者(会社)は従業員に対し安全で健康的に働ける環境を提供する義務、およびハラスメントから守る義務を負っているためです。
まず、労働契約法上の安全配慮義務に照らせば、従業員の心身に過大な負担やストレスを与えないよう配慮することが使用者の責務と定められています 。同法第5条は「使用者は…労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をするものとする」と規定し 、企業は従業員が安心して業務に従事できる環境整備を求められます。助成金制度への対応とは一見無関係に思えるかもしれませんが、もし企業が制度の不明確さゆえに生じる煩雑な手続きを現場担当者個人に丸投げし、過労や極度の心理的プレッシャーを与えているのであれば、それは安全配慮義務違反と評価される可能性があります。例えば、「制度を理解していないと叱責する」「業務時間外に申請書類作成を強いる」といった行為は、従業員の健康を損ないかねません。
次に、職場におけるパワーハラスメント防止義務との関係です。2019年の法改正(労働施策総合推進法改正)により、企業はパワハラを防止するため必要な措置を講じることが義務付けられ、2022年4月からは中小企業も含め全企業でこの義務が完全施行されています 。パワハラとは一般に「優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」で「労働者の就業環境が害される」ものと定義されています 。今回のケースでは、会社が優位な立場を利用して複雑な助成金対応業務を現場社員に押し付け、その結果当該社員の就業環境(精神的安定や職場での安心感)が損なわれていると評価されれば、広義のパワハラに該当しうるでしょう。特に、「助成金を取れなかったら評価を下げる」「自己責任だ」といったプレッシャーを与える行為は、業務上必要な範囲を逸脱した不当な言動とみなされかねません。企業が制度運用の不備によるリスクをすべて現場に転嫁することは、ハラスメント防止の観点からも問題なのです。
要するに、制度の不透明さによる過重な事務作業や心理的負荷を現場従業員に負わせっぱなしにする企業運営は、法律上の「従業員を守る義務」に反する可能性があります。万一メンタル不調や過労が生じ訴訟になれば、安全配慮義務違反・パワハラ容認として企業側が責任を問われるリスクも考えられます。
東証とガバナンス上の問題: 働く人の人権は守られているか
上場企業の姿勢の背後には、東京証券取引所(東証)や投資家からのプレッシャーの欠如も指摘せざるを得ません。東証は企業統治の指針としてコーポレートガバナンス・コードを定めており、2015年の導入以来2021年にも改訂が行われています。このガバナンス・コードでは、サステナビリティ(ESG)への対応として「人権の尊重」や「従業員の健康・職場環境への適切な配慮」が重要な経営課題であると明記されています 。例えば2021年改訂版コードの原則2.3および補充原則2.3.1では、企業が対処すべきサステナビリティ課題の中に「気候変動等の環境問題、人権の尊重、従業員の健康や職場環境における公正で適切な待遇…」が含まれるとされています 。
ところが、現状のリスキリング助成金制度運用に絡む問題—すなわち「国策に従っていれば現場従業員にどんな負荷が及んでも構わない」とも受け取れる企業姿勢—は、ガバナンス・コードの理念から大きく逸脱しているように見えます。本来、東証や投資家コミュニティは上場企業に対し、従業員を含むステークホルダーの人権や待遇に十分配慮するよう促す役割を果たすべきです。しかしこの問題に関して、東証が個別に注意喚起を行ったり、投資家が企業に対し「従業員への過度な負担はリスクである」と指摘したりした動きは明らかになっていません。むしろ、企業が表向き助成金制度を順守している限り、人材育成や人的資本投資の取り組みとして評価されてしまい、その裏で従業員に無理がかかっている事実はガバナンス上黙殺されている恐れがあります。これは東証にとっても看過できない問題のはずです。ガバナンス・コードやディスクロージャー指針でいくら「人権」や「従業員の処遇改善」を掲げても、実際に上場企業がそれに反する運用をしているのを放置すれば、東証自身のガバナンス監督責任が問われます。働く人の人権を守るという観点で、東証や金融当局がこの問題にもっと目を向け、企業に対して是正を促すべきではないでしょうか。
労働者や社会全体に与える悪影響
2025年度からのリスキリング助成金制度とその周辺運用には、現場労働者の犠牲の上に成り立つ構造的な問題が潜んでいます。制度変更自体は手続簡素化の名目でしたが、その副作用として計画段階でのチェック機能が喪失し、現場に不透明で不安定な負担がのしかかっています。それにもかかわらず、企業側も行政側も十分な対策を講じておらず、結果的に弱い立場の現場従業員にシワ寄せが集中している状況です。
この問題に光を当て、是正していくためには、以下のステークホルダーそれぞれの行動が求められます。
労働者・労働組合
現場の声を上げましょう。制度運用で無理が生じている実態や、過重な負担による健康被害の懸念などを労使協議の場で訴え、必要ならば労基署への相談も検討すべきです。「おかしい」と感じたら沈黙せず声を上げることが、制度改善への第一歩になります。
企業経営者・人事責任者
現場任せにせず、制度の不備を正面から捉えてください。助成金ありきで現場に過度なプレッシャーをかけるのではなく、行政に対して制度運用の明確化や改善を要望するくらいの姿勢が求められます。従業員を守ることは長期的には企業価値を守ることにつながると認識し、法的義務を果たすだけでなく積極的に職場環境を整備してください。
政策立案者・行政担当者
現場の混乱に真摯に向き合ってください。制度を形だけ整えるのではなく、利用者目線で運用の透明性や予見性を高める改善策を講じるべきです。例えば事前相談制度の充実やFAQの徹底、公平な救済策の検討など、現場の不安を緩和する措置を早急に検討していただきたい。助成金制度は単なる数字上の成果ではなく、実際に現場で有効に機能して初めて意味があることを忘れないでください。
ESG投資家・株主
人的資本や労働慣行にも目を向けてください。企業のサステナビリティ報告や統合報告書で、従業員への負担や職場環境について適切に開示しているかをチェックし、疑問があれば経営陣に問い質すべきです。従業員を大切にしない企業は長期的なリスクを孕むとの視点から、労働者の人権を軽視するような制度運用を黙認しないという明確なメッセージを送りましょう。
東京証券取引所・監督当局
ガバナンス・コードの精神を具体的な行動につなげてください。上場企業に対し、従業員の適切な待遇や人権尊重が確保されているかをモニタリングし、不適切な事例には改善を促す仕組みが必要です。企業が国策の名の下に従業員を酷使していないか、ESGの観点で厳しく評価することも東証の社会的責任ではないでしょうか。
結論として、本制度の運用上の問題点は一企業や一労働者の問題に留まらず、日本の労働政策や企業ガバナンス全体に関わる課題です。 労働者が安心してスキルアップに取り組める環境を整えることこそが本来の「人への投資」のあるべき姿のはずです。不明確で不公平な助成金制度運用によって現場に犠牲を強いる現状を直ちに改め、誰もが安心してリスキリングに挑戦できる公正な制度設計への見直しが強く求められます。それはひいては日本企業の競争力向上にも資するものであり、労使と行政、そして市場が一体となって実現すべき社会的正義の課題と言えるでしょう。

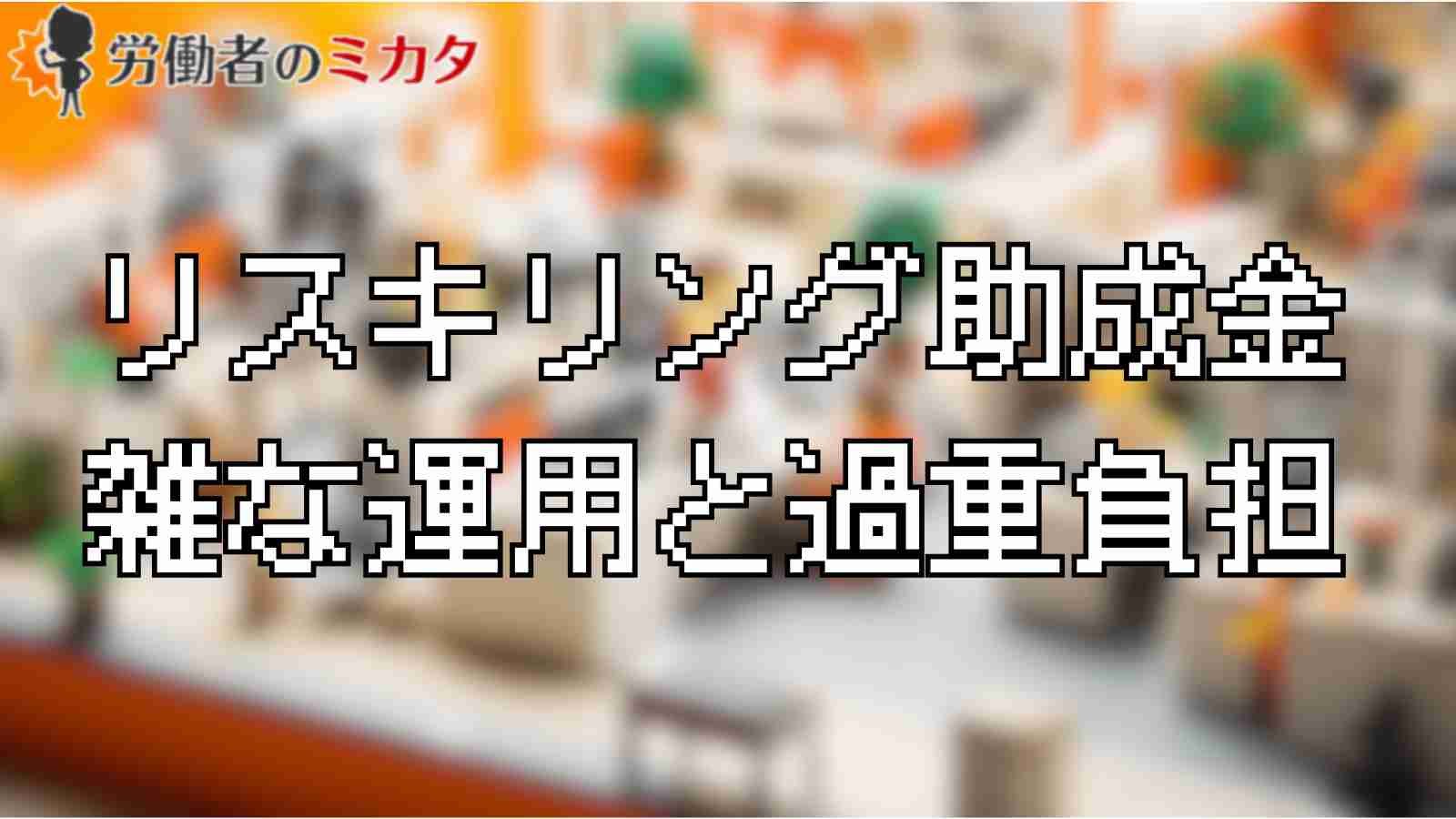
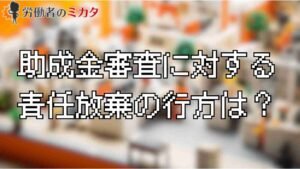

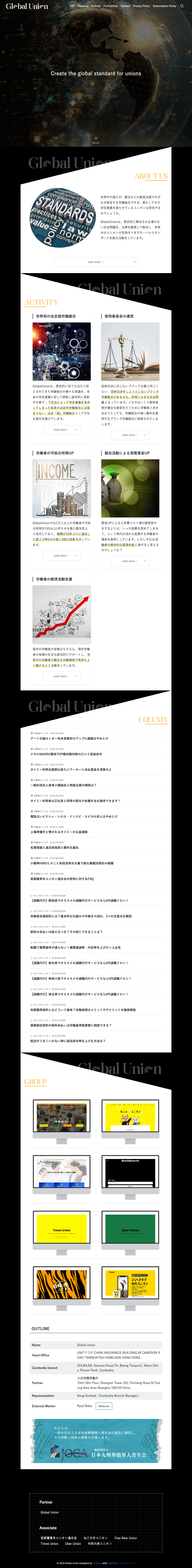
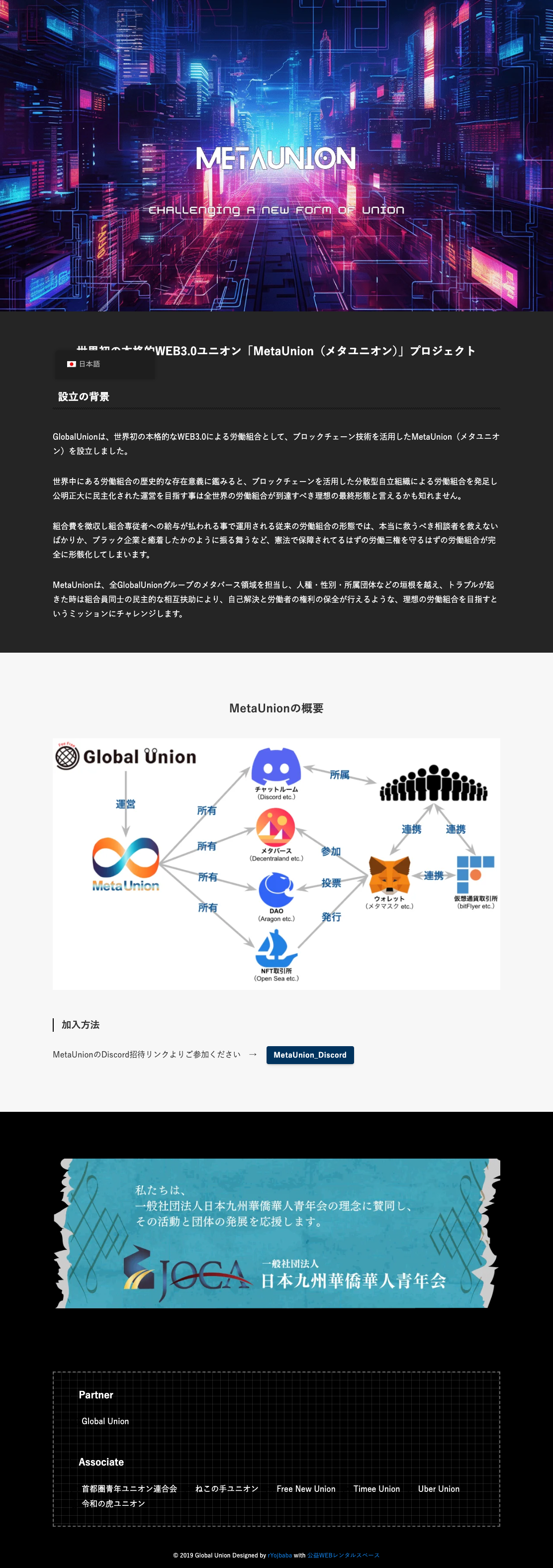
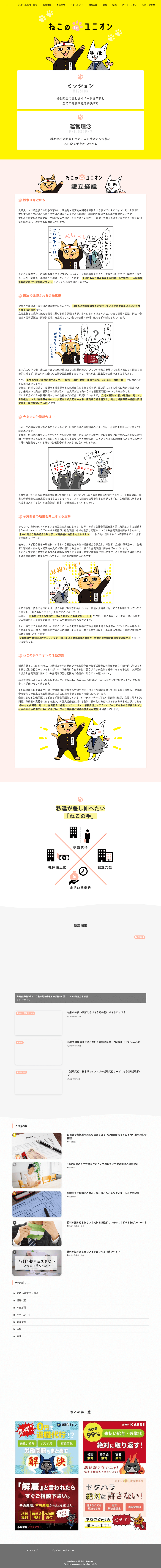
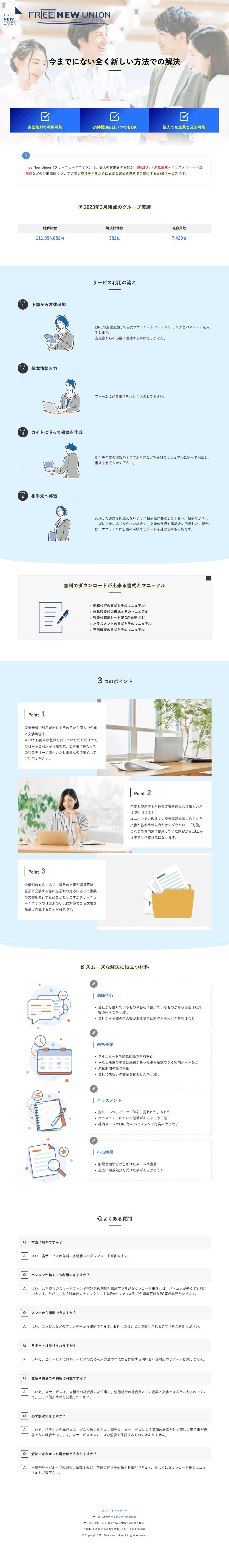
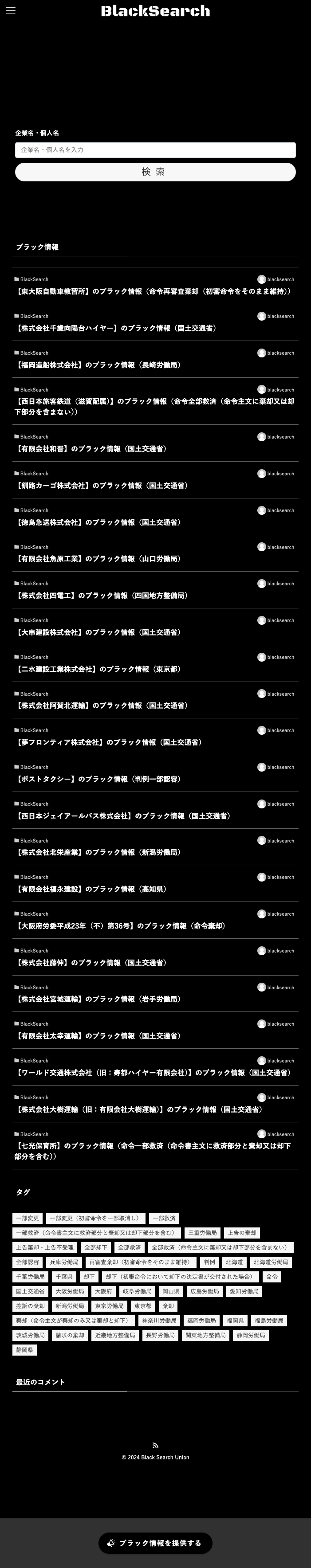
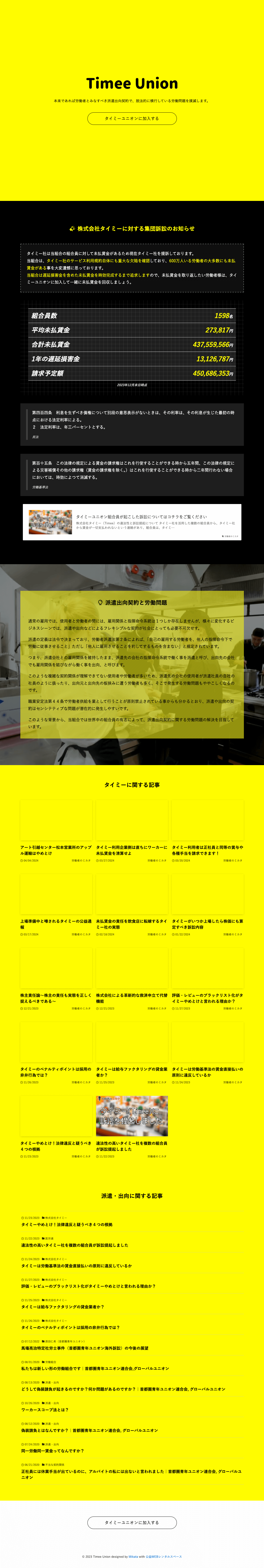

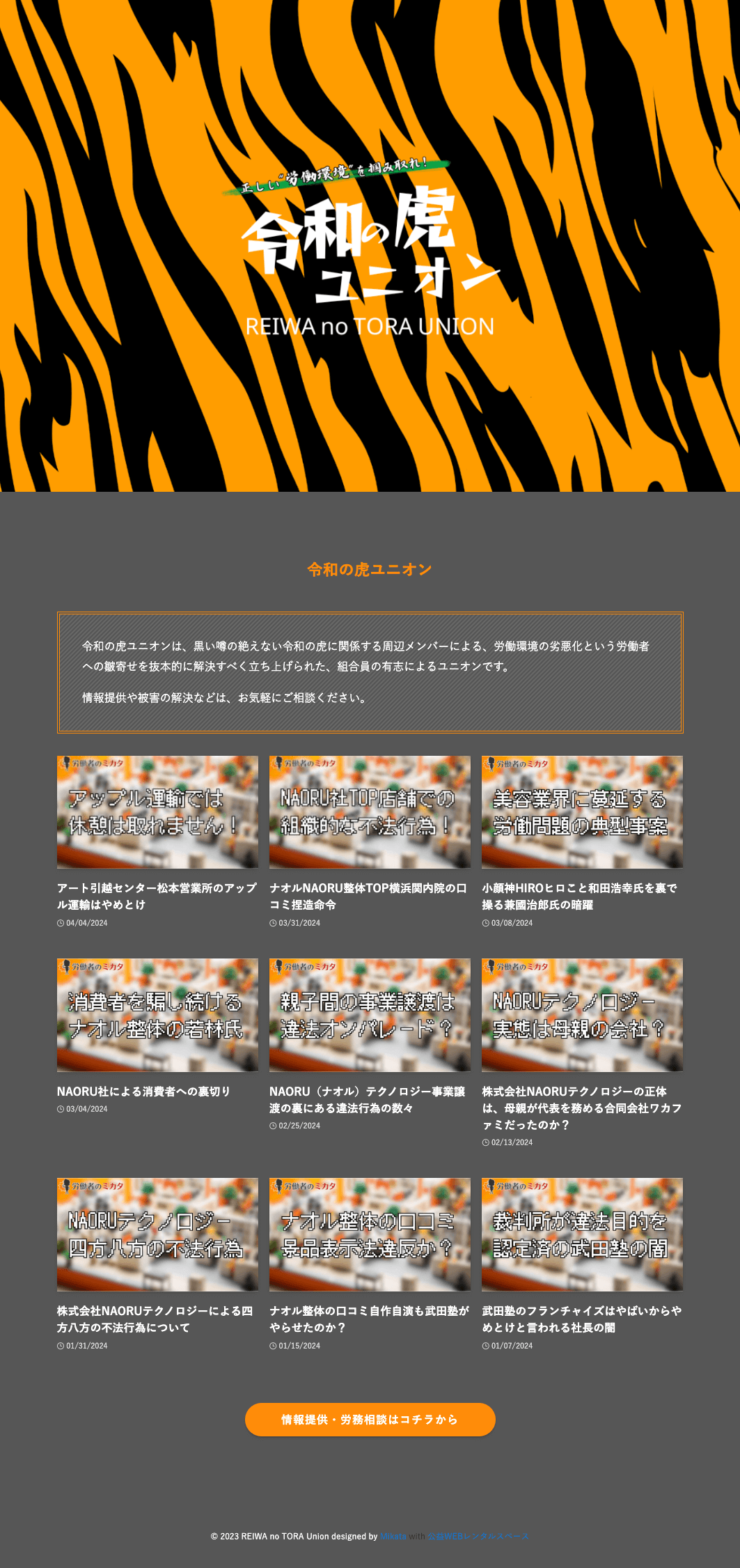
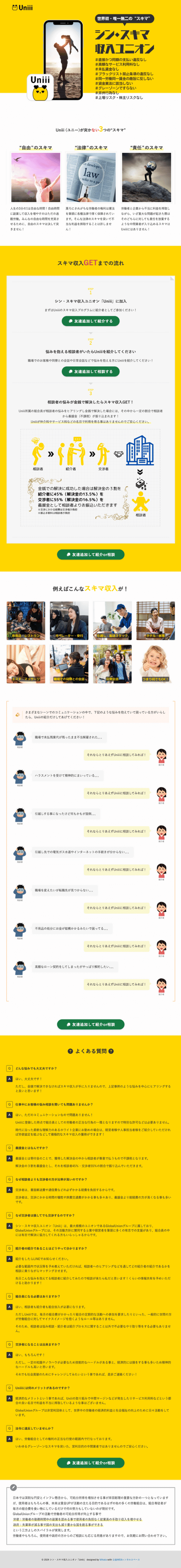
コメント