「助成金の“門番”やめました」では済まされない。
計画届“ノールック”審査方針に見る、労働局の怠慢と制度の空洞化
2025年度から、厚生労働省はリスキリングを対象とした助成金制度に関して、計画届の段階では一切審査を行わず、支給申請段階でまとめて審査するという新たな運用方針を打ち出しました。これにより、企業や現場担当者は数ヶ月後の「支給申請」まで“宙ぶらりん”のまま制度適用の可否も分からず準備・投資を進めなければならないという、著しく不透明で理不尽な運用が常態化することとなります。
かつては“見ていた”。今は“見ない”。それでも様式はほぼ同じ。
これまで、労働局は計画届に対して明確にチェックを行っており、実際に形式的な不備や一部構成要素のみを根拠に受理を拒否する事例が多発していました。
しかし今期より、「計画届は単なる提出物であり、審査は支給申請時に行う」との方針が示されたことで、実質的な審査責任を先送りしたまま、形式上だけ“受付は自由”という建前が前面に出されるようになりました。
にもかかわらず、様式自体は変更されていないのです。
つまり、提出される文書の内容は以前と同じであるにもかかわらず、「今は見ない」という姿勢に転換した労働局の対応は、単なる事務の簡略化ではなく“行政責任の回避”に他なりません。
「国民に広く資する制度」である以上、説明責任は免れない
リスキリング助成金制度は、デジタル人材育成や産業構造転換に不可欠な国家的再投資スキームであり、特定企業や特定労働者のための制度ではなく、“社会全体の雇用基盤を支える”ための公的インフラです。
そのような制度において、「見ない」「判断しない」「先に進め」とだけ言いながら、後日一括して不支給処分を下す運用は、制度設計の理念にも行政機関としての責務にも明らかに反します。
現場の担当者を“ハラスメントの矢面”に立たせる構造
さらに深刻なのは、この不明確な制度運用によって、企業内で助成金対応を任された労働者(多くは人事・総務職)に過剰な負担と精神的圧力がかかっているという点です。
「これは使える」「これはダメ」と恣意的に拒否される中で、労働局からの高圧的な言動や、不明瞭な審査基準による人格否定的な指導を受けたという声も多数寄せられています。
このような状況は、制度の名を借りた行政機関による“指導型ハラスメント”であり、重大な人権問題です。
無料の労働組合が、広く現場の声を代弁します。
私たち無料の労働組合は、これまで数多くの労働者の声を拾い上げてきました。
この制度変更により困っている方、あるいは労働局からの対応に疑問や不快を感じている方は、一人で抱え込まず、ぜひ当組合にご相談ください。
労働者が声を上げることでしか、制度の健全な運用は守られません。
リスキリング助成金制度を「本当に役立つ制度」にするために、共に声を届けましょう。
制度改正を要求するための行政監視チームの立ち上げ
今後、各労働局ごとの対応差や不受理事例の集積分析、制度改正を要求するための行政監視チームの立ち上げを検討しています。
ご賛同いただける方は、ぜひ組合の窓口へご連絡ください。

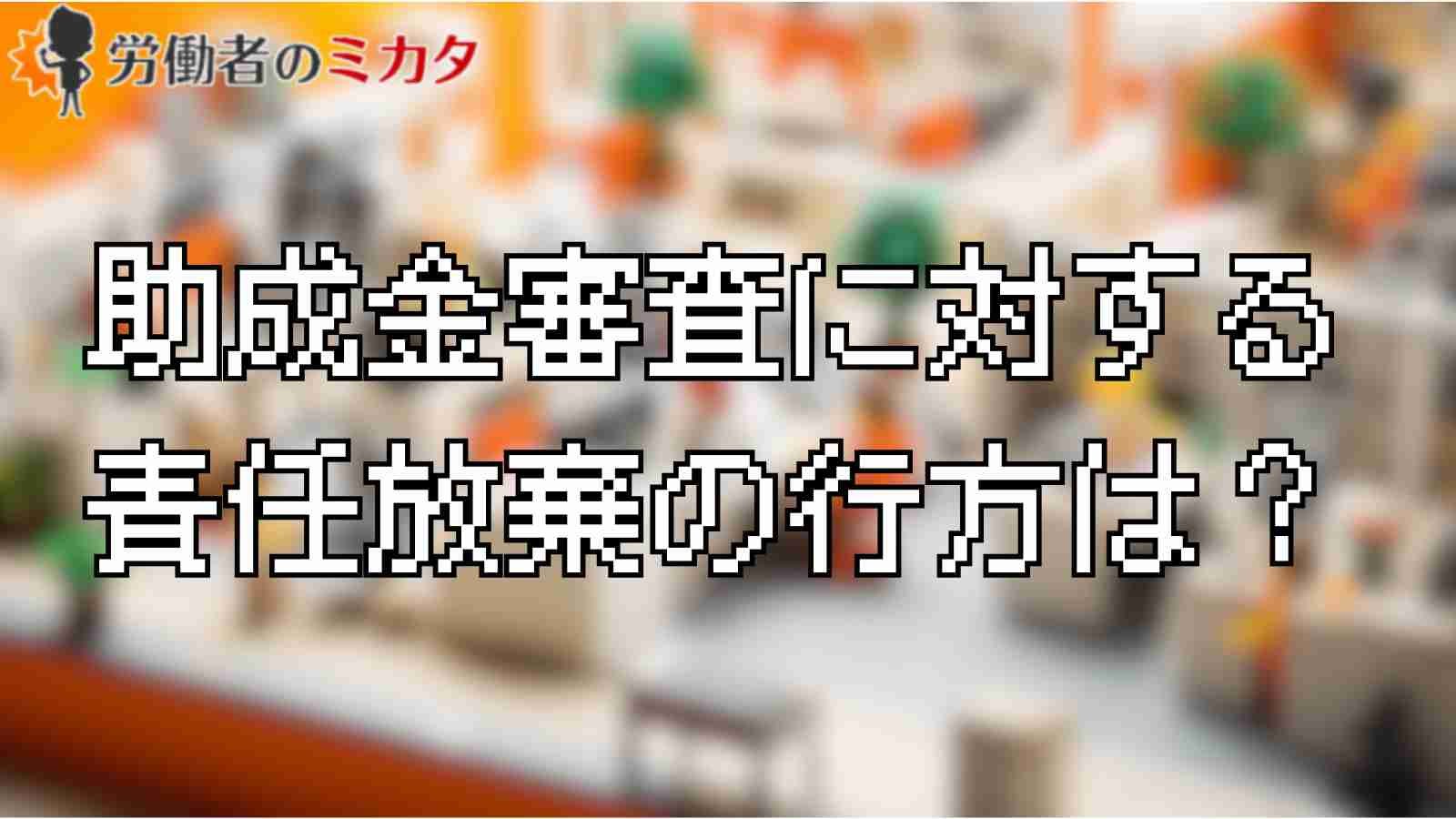


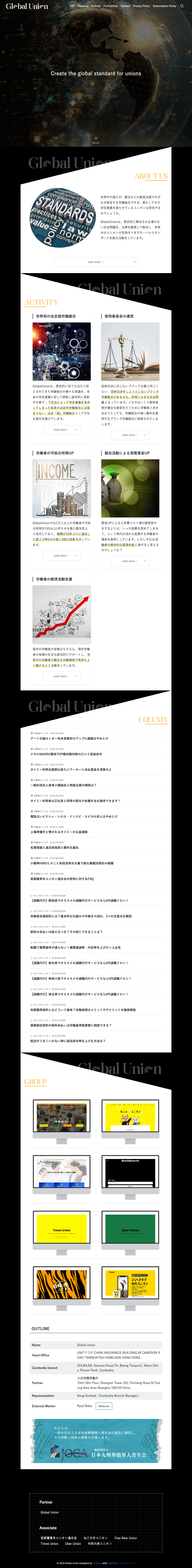
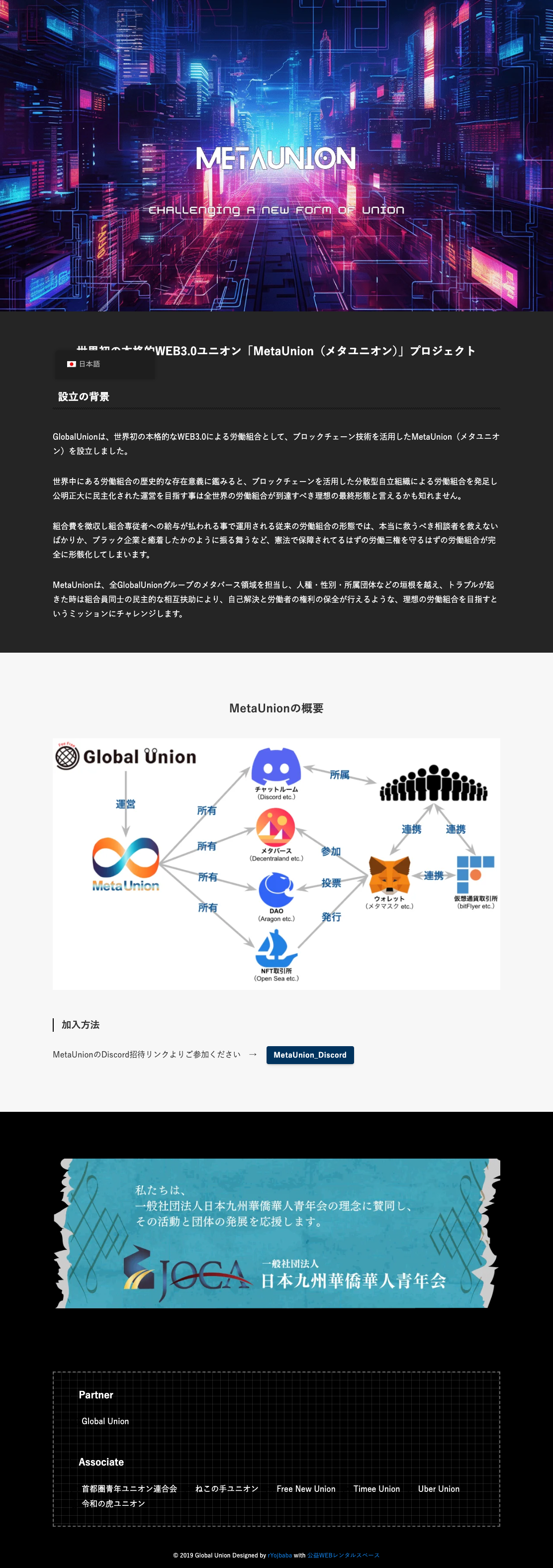
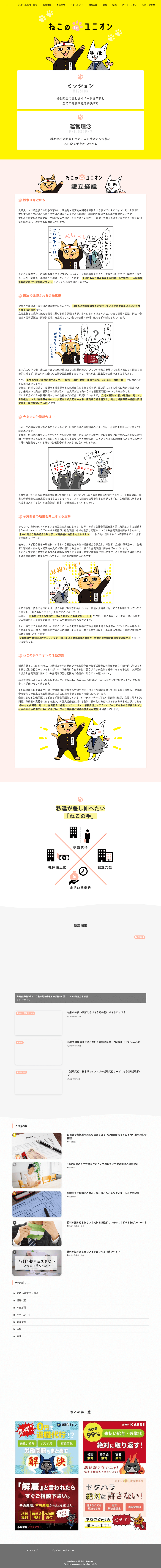
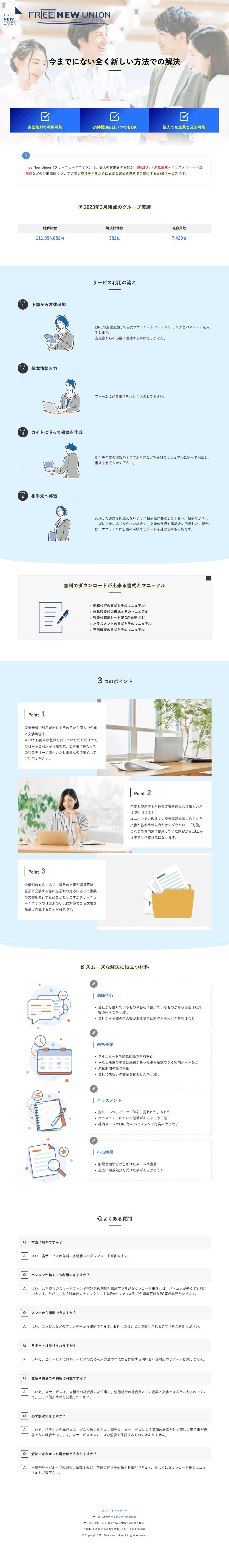
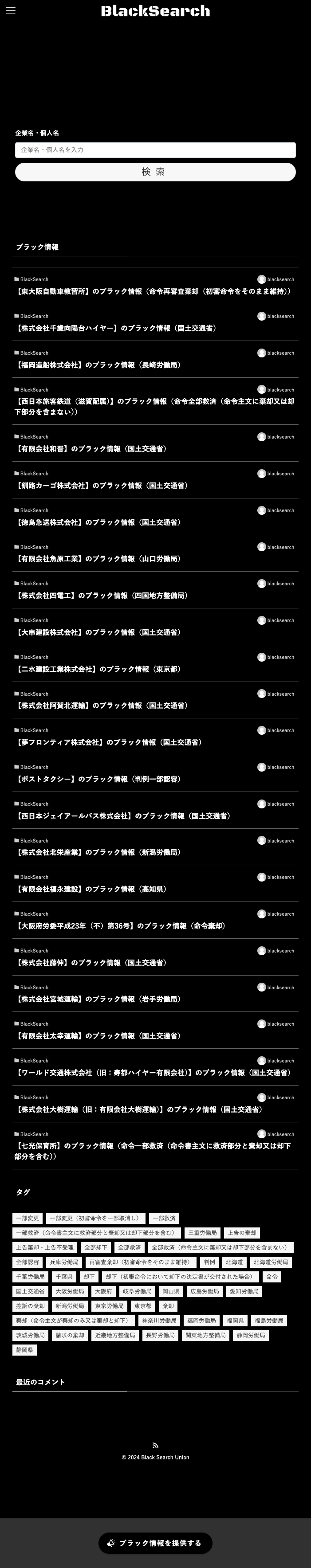
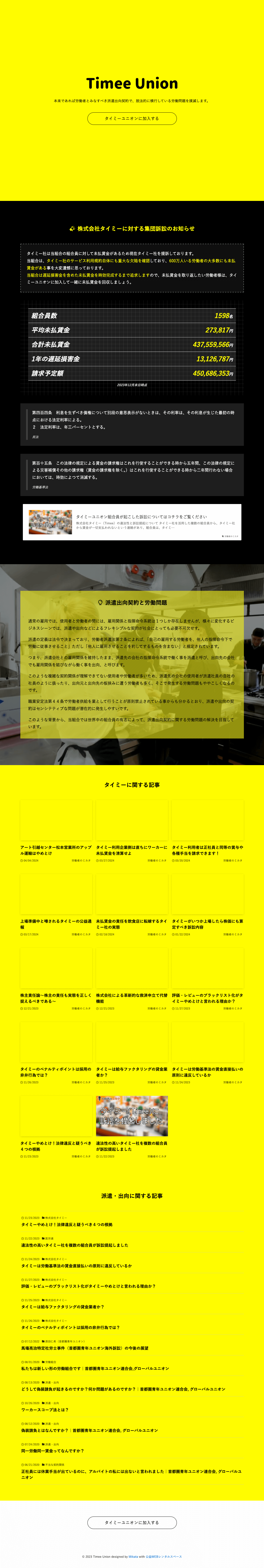

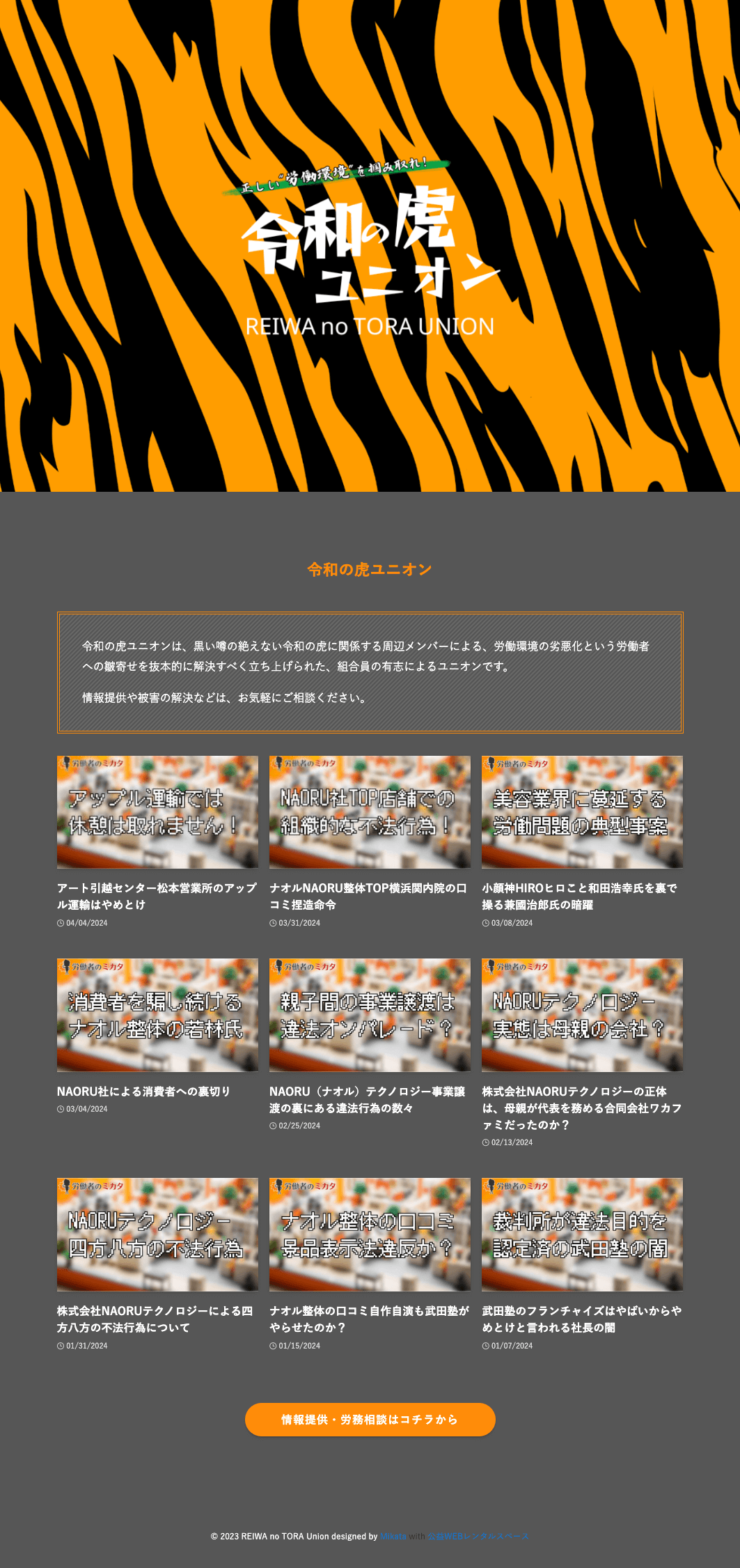
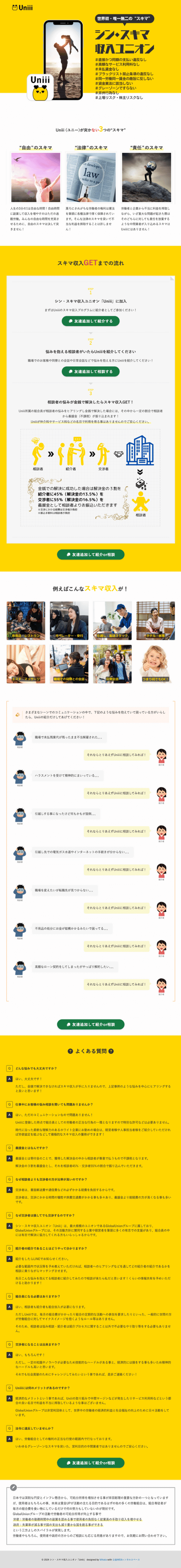
コメント